「経営事項審査」の必要書類は?
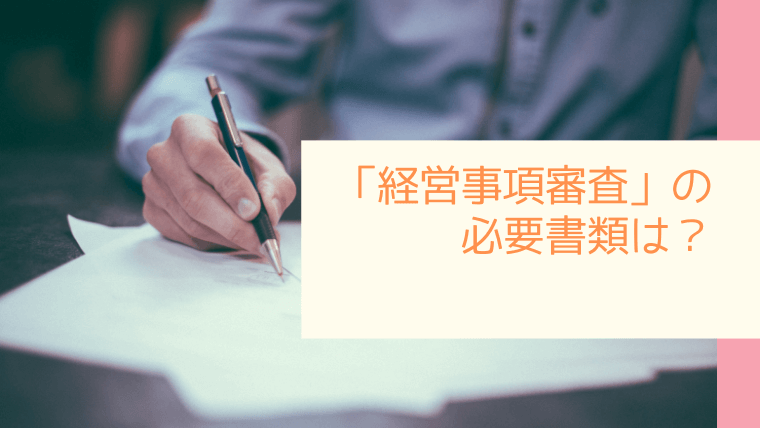
「経営事項審査」の必要書類は、建設業許可の必要書類とは異なります。
「経営事項審査とは何ぞや?」という方は、以下のリンクにて記載しています。
提出方法に決まりはあるの?
届出書類は、正本・副本の2部作成する必要があるよ。
経営事項審査の必要書類は?
「経営事項審査」で、基本となる必要書類を紹介しています。
イレギュラーなケースでは、別途必要書類が必要となることがあります。
以下では、必ず必要となる書類は、赤色にしています。
状況により必要となる書類は、青色にしました。
経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の表紙【府様式第1号】
正本・副本ともに、表紙は必ず必要です!!
経営規模等評価申請書・総合評定値請求書【25号の11】
申請書を書くのは基本なので、必ず必要です!!
書き方は、以下のページで紹介しています。
工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高【別紙1】
完成工事高で評価するので、必ず必要です!!
書き方は、以下のページで紹介しています。
工事種類別完成工事高付表【国交省第1号】
振替(参入)をするときに、必要な書類です。
振替(参入)をしなければ不要です。
振替(参入)については、以下のページで紹介しています。
技術職員名簿【別紙2】
技術職員は評価に影響するため、必ず必要です!!
書き方は、以下のページで紹介しています。
継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿【国交省第3号】
雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も雇用する制度です。
65歳以下の者に限ります。
継続雇用制度の適用を受けている技術職員がいなければ、必要ありません。
継続雇用制度の適用を受けている人がおり、常時10人以上の労働者を使用している法人は、「継続雇用制度について定めた就業規則の写し」が必要になります。
労基署受付印は必要で、提出では「表紙」と「継続雇用制度を定めた部分」のみでOKです!!
審査基準日の6カ月以内に定年退職し、再雇用した場合は、連続雇用の確認が必要です。
「社会保険資格の取得・喪失証明書」(取得と喪失は同日)が必要です。
その他の審査項目(社会性等)【別紙3】
社会性は評価に影響するため、必ず必要です!!
書き方は、以下のページで紹介しています。
工事経歴書【2号】
工事経歴書は、建設業者の実績を証明になので必ず必要です!!
工事実績なしでも、受審する業種は必要です。
書き方は、以下のページで紹介しています。
工事経歴書記載の上位5件分の、「建設工事に係る契約書、注文書、請書等の写し」も工事実績を証明するのに必要です。
工事実績がない場合は、証明しようがないため不要です。
ちなみに公共工事では発注者印が必要ですが、もしなければ入金確認資料などが必要となります。
単価契約書や年間契約書の場合は、請負金額のわかる指示書の写しが必要です。
経理処理の適正を確認した旨の書類(原本)【国交省第2号】
「その他の審査項目(社会性等)」の「(項番52)監査の受審状況」にて、裏付資料と提出します。
関係なければ不要です。
ISO9001又はISO14001の規格による登録されていることを証明する書類の写し
「その他の審査項目(社会性等)」の「(項番57)ISO9001の登録の有無」と「(項番58)ISO14001の登録の有無」にて、裏付資料と提出します。
関係なければ不要です。
経営状況分析結果通知書の原本
経営事項審査を受審する前に、国土交通大臣から登録を受けた指定の民間企業から「経営状況分析結果通知書」が必ず必要です!!
委任状の原本
行政書士などが代理申請する場合に、必ず必要とします。
建設業者自身で申請する場合は、不要です。
委任事項が間違えていることに備えて、申請者さんに説明したうえで捨て印をもらっておいたほうがよいでしょう。
国家資格等を確認する書類の写し
前回の経営事項審査から変更があった場合や、まだ申請をしていない場合に技術職員の資格証明として必要です。
前回に提出済みで、今回も同じ場合には不要です。
技術職員実務経験申立書【府様式第2号】
前回の経営事項審査から変更があった場合や、まだ申請をしていない場合に技術職員の実務証明として必要です。
前回に提出済みで、今回も同じ場合には不要です。
技術職員名簿に記載されている職員の審査基準日以前6か月を超える恒常的雇用関係及び常時雇用を確認できる書類
法人や個人、役員や従業員などで、提出する資料が変わってきます。
技術職員がいなければ、不要です。
法人の場合は、以下の書類が必要です。
- 法人税確定申告書のうち「役員報酬手当等及び人件費の内訳」
- 決算報告書のうち一般管理費及び工事等原価報告書(報酬・給与・賃金額がわかるもの)
個人事業主は、以下の書類が必要です。
- 所得税確定申告書のうち収支内訳書と第二表、又は青色申告決算書(専従者給与額及び給与支払者の給料賃金額(個別の内訳がわかるもの))
- 国民健康被保険者証
- 住民税課税証明書(直近分)
個人事業主以外の技術職員
源泉徴収簿または賃金台帳で、審査基準日以前6か月を超える期間分が必要です。
賃金額が10万円未満の場合、別途必要書類が必要になり、従業員の場合は技術職員になることはできません。
個人事業主と専従者以外の技術職員
以下のどれかを提出が必要です。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、及び健康保険被保険者証
- 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人交付分)
- 船員保険被保険者証
この辺はややこしいのですが、後期高齢者や出向社員などの条件で、必要書類が別途必要になります。
技術職員名簿に記載されている若年技術職員の生年月日を確認できる、官公庁又は公的機関・団体が発行した書類の写し
「若年技術職員」とは、審査基準日時点で満35歳未満で技術職員名簿に記載されている技術のことです。
健康保険被保険者証などの写しが必要ですが、「恒常的雇用関係及び常時雇用を確認できる書類」を提出するので問題ないでしょう。
建設機械の保有状況一覧表【府様式第3号】
「その他の審査項目(社会性等)」の「(項番56)建設機械の所有及びリース台数」にて、裏付資料と提出します。
関係なければ不要です。
「建設機械の写真」や「リース状況が確認できる書類」なども状況により必要です。
国土交通大臣による外国子会社、並びに建設業者及び外国子会社についての数値の認定書写し
日本にある親会社と外国にある小会社に係る数値を、国土交通大臣が認定し評価します。
この制度を利用する場合は、事前に国土交通大臣の認定申請を行い、数値の認定書を受領することが必要になります。
関係なければ不要です。
提出書類は状況により、他にも必要となる書類があったり複雑です。
経営事項審査の提示書類は?
提出書類のほかに、申請内容を確認するための提示書類も必要となります。
必ず必要となる書類は、赤色にしています。
状況により必要となる書類は、青色にしています。
- 建設業許可通知書又は許可証明書の写し(申請日現在有効なもの)
- 建設業許可申請書副本一式(申請日現在有効なもの)
- 決算変更届副本一式(審査対象事業年度及び完成工事高計算基準の区分に応じた年度分のもの)
- 変更届副本一式(直近の建設業許可申請(新規又は更新)以降に提出したもの)
- 経営規模等評価申請書副本一式及び経営規模等評価結果通知書(前期分)の写し
- 審査対象事業年度及び前審査対象事業年度に係る法人税確定申告書別表十六(一)及び(二)、また、必要に応じて、別表十六(五)、(六)及びその他減価償却実施額が確認できる書類の写し
- 完成工事高を確認できる書類であって、審査対象事業年度及び完成工事高計算基準の区分に応じた年度分に係る書類の写し
- 審査基準日現在の雇用保険の加入の有無を確認できる書類の写し
- 雇用保険が適用除外の場合の書類の写し
- 健康保険及び厚生年金保険の加入の有無を確認できる書類
- 建設国保、大建国保等の建設国保に加入の場合の書類の写し
- 建設国保及び大建国保に未加入で健康保険及び厚生年金保険適用除外を確認できる書類の写し
- 建退共の大阪府支部発行の建設業退職金共済事業加入・履行証明書の写し
- 企業年金制度又は退職一時金制度導入の有無を確認できる書類の写し
- 法定外労働災害補償制度の加入の有無を確認できる書類の写し
- 防災活動への貢献状況を確認できる書類の写し
- 監査の受審状況を確認できる書類
- 研究開発費の状況を証する書類のうち額を確認できる書類であり、かつ、有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない会社は有価証券報告書の写し
- 技術職員名簿に記載されている職員のうち新規若年技術職員の育成及び確保の状況を確認できる書類
必要書類が多すぎて、わけわからんわ。
面倒であれば、経営事項審査に詳しい行政書士に頼むのもアリですね。